お疲れ様です。タケウチです。
自分が嫌いという人は少なくありません。どうして怠けてしまうのか、どうして物事を続けられないのか、どうして自分はコミュ障なのかと、ぐるぐると自己嫌悪に陥る。こんなことってありますよね。
かく言う私もそうで、死ぬまでは自分と付き合い続けなければならないのに、自分が嫌いという思いに悩んできました。
最近、カウンセリングや心理学を勉強する中で、これで自分が嫌いという状態をなんとかできるのではないかと思える方法を見つけましたので、この記事でシェアしていきたいと思います。
自分が嫌いな自分をも肯定してあげる「どんな自分もOK法」
ポジティブの本来の意味
多くの日本人はポジティブを勘違いしています。
コップに半分ぐらい水が入っていて、「半分も入っている」と思った人はポジティブ、「半分しか入っていない」と思った人はネガティブという話がありますよね。
これは大嘘です。
ポジティブとは、「YES!」という意味。上の例えでいえば、「コップに水が入っている」が本来のポジティブの考え方なんです。その状態のまま肯定するイメージですね。
これってこの現代社会でよく聞くある言葉に繋がると思いませんか?そうです。
「自己肯定感」ですね。
本来の自己肯定とは?
自己肯定とは、「今日は○○ができたから自分は偉い」とか「~~しているから自分を褒める」など条件付きの肯定とは違います。だってできてないときは肯定できないんだから。
「自己肯定感」は、「どんな自分でもOKと思える」というもの。まさに自分を「Yes」と言うことなんです。
条件を満たさないと自己否定してしまう人は、幼い頃に親や先生から、「ちゃんと勉強ができるから偉い」「笑顔が可愛いから愛したい」など、条件付きの愛を与えられてきたことが影響しています。
条件付きの愛や肯定は諸刃の剣です。条件を満たせているときは良いですが、ひとたび条件を満たせなくなると、自分を肯定できなくなってしまう。例えば、「勉強ができていない自分」「人に親切にできない自分」「ちょっとしたことでイライラしてしまう自分」が現われるそんな自分はダメだと思ってしまうわけですね。
フロイトの精神医学
自分を否定している自分が、自分と一体化しているのって分かりますか?ちょっと分かりづらいですね。
「~べき」と命令してくる、ある種無慈悲で完璧な自分。それを超自我と呼びます。これは自分ではありますが、自分の中で誰かが息づいていることが多くあります。昔から自分に考えをすり込んできた誰かです。多くの場合は親ですね。
次に、無意識レベル素直に感じる自分、ネガティブな感情もわきやすい自分、「こうしたい」「ああしたい」という欲望に従う自分。これをエスと呼びます。
最後に、自分を無意識に客観視している自分、これを自我と呼びましょう。
自己肯定感を上げるには、最後の自我を意識してみると上手くいきます。
先ほどの「自分を否定している自分が、自分と一体化している」というのは、「エスを否定している超自我と、普段は無意識の自我が癒着をしてしまっている」という意味です。超自我と自我が一緒になって、エスを否定してしまっている。
これが自己嫌悪の正体です。
どんな自分もOK法
上記で自分が自分を嫌ってしまう状態の仕組みが理解できたかと思います。なんとなーく分かって頂ければ結構です。
では、そういう自己肯定感が低い状態を改善するにはどうすればいいか。その方法は案外簡単なものです。
それは「どんな自分でも「OK」を出す」というもの。
例えば、「今日は仕事から帰ってきてだらだらしてしまった。なんて怠惰でダメ人間なんだ。もう嫌だ。」と思ったとします。
そこで、「そんな自分もOK」と唱えるのです。
ポイントは、「ああ嫌だなんて思ってしまった、自己肯定できていない」と二重の否定をしないことです。
つまり、上記のエスを否定しないことはもちろんですが、超自我も否定しないということ。
超自我とエスという意識に挟まれた、自我という意識を認識して、橋渡しをするようにどちらも肯定してあげましょう。
「自分(エス)が嫌いな自分(超自我)」まるごと肯定をする。どんな自分でもOKとはそういうことです。
まとめ
いかがでしたか。
これを知ったとき目から鱗でした。しかも、上記の「意識」について、100年以上も前にフロイトという研究者が解説しているということ。すごいよね。
また、自己肯定感を上げるにはどうすればいいか、ということについて発信をしていきます。ブックマークなんかに登録していてもらえると嬉しいです。それではまた。











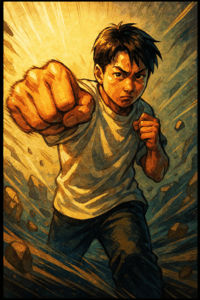
コメントを残す