全国の学校で必須の教科にするべき。え?どんな教科かって?
それは「自己理解」です。意味は分かるけど聞きなじみのない言葉でしょう。
学校や親に教えてもらうことはないからです。
しかし、これを学校で教え、子どもの時から「自己理解」をすることで、世間のしがらみや違和感から解放され、幸福を感じる人が増えるだろうと確信しています。
そんな「自己理解」の教科書ともいえる、八木仁平さんの本「世界一やさしい本当にやりたいことの見つけ方」は見える世界を一気に変えてくれました。
・私がエレクトーンを16年続けられているのは、毎日コツコツやって、物事を完成品に持ってくのが大好きだからだと知れた。
・バイトが2ヶ月しか持たなかったのは、周りのことを自分で決めたいという欲があったからだと知れた。
・「教える」という行為がすごく得意なことに気づく&やりたいことも見つかった
・飽き性なのが悩みだったが、新しいことをどんどん学んでいきたいという強みの表れだった。
・人のことをうらやむことがなくなった
一冊の本が一人の人生を大きく変えることはよくあります。やっていたことにモヤモヤを感じていた私はこの本に救われました。
この本にはワークがついていて、じっくりやっていくと、自分の価値観、得意なこと、好きなことが導出されます。これだけでも自分のことがよく分かります。
さらにこれらをパズルのように組み合わせていくことで、「本当にやりたいこと」を見つけることができ、自分探しの旅に終止符を打つことができるのです。
私は、要領も悪いし、特段才能もなくて、上下関係も苦手だったので、社会不適合者だと思っていました。こんな自分にやれることなんてあるのかと思っていました。
しかし、この本のおかげで「本当にやりたいこと」が見つかり、人生がわくわくしてしょうがありません。また、他人のマシンガンに憧れることなく、自分の小さなナイフを大好きになることができました。
世界一やさしい本当にやりたいことの見つけ方はどんな本?

数学のように自分のやりたいことを導き出す本
世の中の自己啓発本は「やりたいことをやれ!」「役立つことをしていれば結果はあとからついてくる」「お金のことなんて考えるな」という、正しいけれど、実行できそうにないアドバイスをしてきます。
勇気をもらえるし、人生に希望が差し込みます。読んだ直後は、わくわくします。しかし、一時的にやる気がでて、その通りにやっても、結局迷走してしまうことが多いんですよね。
この本は違います。
「直感的」ではなく、「論理的に」やりたいことを導けるのです。
「やりたいこと」が導出される様はまさに数学です。数学は公式さえ覚えてしまえば、あとは応用で解ける科目です。個人差はあれど誰でもできます。
つまりこの「自己理解」という科目は、誰でも、必ずできるのです。
自己理解って何?
この本では、「自己理解」がメインテーマです。その名の通り、自分を理解することなんです。そんなことしてなにになるんだと思うことでしょう。「自分のことくらい知っている」と。
でも、実際みんな「自分のことをよく分かっていない」のです。
例えば、
私は「リーダー」や「素晴らしい曲をつくる作曲家」に憧れたことがあります。学級委員長に立候補してみたり、自分の曲をどんどんつくってやろうと意気込んでみたりしました。
ことごとく失敗しました。学級委員にはなれなかったし、曲も今までに4曲しかつくってません。
でも当たり前でした。みんなを引っ張ることが得意でもなければ、0からなにかを作り出すことも苦手でした。小学校の「図工」や中学校の「美術」で良い成績をとったことはありません。
しかし、無意識にやれていたこともありました。困っている人を助けたり、さらっと人のミスをフォローしてみたりすること。曲の構成を書き換えたりする「編曲」は、なぜか夢中でできる。
なんの努力もいらなかったので、認識していませんでした。「得意だ」という自覚もなかったのです。
この本のワークによって、私はその強みを認識させられました。そして自分のことをよく知らなかったことも。
「共感力」や、「コツコツやっていって完成品に近づけるのが好き」というのは才能だったのです。
ストレングス・ファインダーという自分の強みを見つける本には、こういう話が書かれています。(自分の強みが5つでるので、八木さんの本と併用するのがオススメです。)
「聖ペテロ、私はずっと軍の歴史に関心がありました。だれが史上最高のの将軍ですか?」
「簡単だ。あそこにいる男だよ。」
「何かの間違いでしょう?彼とは地上で知り合いましたが、ただの労働者でしたよ。」
「友よ、その通りだ。彼は史上最高の将軍だった。もし彼が将軍になっていたらね。」
自分の強みに気づいて、それに合う仕事についていれば、彼は最高の将軍になっていたはずです。この話は、「「強み」を認識して、どんどん活かすべきだ。そうでなければ、、、」というのを、上手く伝えてくれるのです。
「自分の強み」に気づかなければ、自分に合わない作業や仕事をするはめになります。人の才能に憧れ、自分を卑下することになります。そして、無駄な努力を重ね、一生を過ごすことになります。
「自己理解」とは自分の人生をより豊かにするために「自分をよく知る」作業なのです。
なぜ本当にやりたいことを見つけるのが大事なのか?
人生100年時代。今小学生くらいの子達は、半分の人が100歳まで生きるそうです。
少子高齢化もあって、私達は多分年金がもらえません。22、23歳から死ぬまで働き続けなければならないのです。
どんな仕事をしたいですか?やりたくもないしんどい仕事をするのって考えただけでもぞっとしませんか?
しかし、学校や親に「仕事は我慢だ」とか「働かざる者食うべからず」と言われるせいで、「仕事=苦しい」「我慢=お金」と思っている人が多いです。
そしてどこかで「やりたいことをやるなんて甘えだ」と思っているでしょう。そのせいか「やりたいこと」がない人もいると思います。
しかし、死ぬまで働かなければならない時代だからこそ「本当にやりたいこと」を見つけることが必要なのです。
「やりたいこと」を見つけると面白いことが起きます。
・「やりたいこと」を学び、成長する。
・学んだことを人に提供し、お金と感謝をセットで受け取る
・そのお金を、また学びに投資する
・そして、成長したスキルでより高い報酬を受け取る
学び、成長、報酬という無限ループが生まれるのです。
これなら仕事がストレスになりません。死ぬまで働けます。むしろ働いているという自覚もないかもしれません。ホリエモンがよくいう「遊び」になるでしょう。
世界一やさしい本当にやりたいことの見つけ方を読むとどうなるか

他人に憧れなくなる

「クリエイティビティ」とか「リーダーシップ」とか「コミュニケーション力」とか、かっこいいです。こういう才能は目立つので、だれもが憧れますよね。
また、学校や社会ではアホみたいに、クリエイティビティのような才能を褒めまくる傾向にあります。そして、「役立たない才能」を切り捨てます。
本当は才能なのに「短所」のように扱うことも多いです。そしてそれを「克服しろ」と強制してきます。
よく考えたら洗脳です。
特定の才能だけが偉いなら、みんながみんな言いたいことを言うとか、みんなリーダーみたいに我が強いとか、人脈はあるけど、関係が浅い友達ばっかりみたいな現象を褒め称えることになります。
社会が回っているのは、才能が才能をカバーし合ってバランスを保っているからです。目立たないものでも、立派な才能です。
この本で「得意なこと」を導出すると、そういう地味な才能に気づけます。
私の強みは「共感力」「狭く濃く関係を築くこと」「目標に向かってコツコツやること」「学ぶこと」「自分で身の回りのことを決めること」です。
すげえ地味です。
短所にも置き換えやすいですよね。「すぐ泣く」「友達が多くない」「上下関係が苦手」「上から命令されたことをこなすのが苦手」。だから、今まで才能がないと思い込んでいました。
しかし、強みが認識できたら、
・無理に新しい友達を作るのは辞めたし
・バイトが続かないのは、そもそも他人にとやかく言われるのは嫌いだからだし
・コツコツやれるからブログを1年続けてるわけだし
・飽き性なのは新しいことをどんどん学びたいからだし、
・泣き虫なのは共感する力があるから
だと思えました。
自分を認めることができると何が起こるか。他人に憧れなくなるのです。
自分の持っている小さなナイフを大切にしようと思えます。そして、それをどんどん磨いていこうとも思えるのです。
そして、自分の強みを上手く活用できていると、他人に憧れないし、そのおかげでストレスがなくなります。どんどん上達するので、楽しくなるし、自信がつきます。
自分の「軸」が分かり、本当にやりたいことが見つかる

「つぶしがきくから法学部」とか「今稼げるからプログラミング」とか、「将来役立ちそうだから勉強する」とか、やりたいことが分からずに迷走することがなくなります。
まず、迷走する原因としては、実現手段(Do)から考えてしまうことです。できること(Do)、好きなこと(like)、持っているもの(have)、どうあるべきか(Be)の順で考えてしまうのです。
職業に自分をあわせに行っている状態です。シンデレラに出てくる意地悪な人達が、王子と結婚しようと、自分の足をガラスの靴に合わせて切っているのと同じです。
シンデレラフィットできていないので、これって本当にやりたいのか、、、と悩むことになります。
八木さんの本では、どうあるべきか(Be)、持っているもの(have)、好きなこと(like)、できること(Do)の順で考えます。
どうあるべきかというのは、自分の価値観です。例えば、「自由にくらしたい」「好きなことに情熱を注ぎたい」「シンプルな生活をしたい」「美を追究したい」などなど。
そして、持っているもの(自分の強み)と好きなこと(情熱)を掛け合わせ、やりたいことを見つけていきます。情熱は強みを磨く上でも大切です。
「IT」や「スタンドバイミー」で有名なホラー作家のスティーブン・キングは、こう言っています。
「楽しくなければなにをやっても無駄である」
書くのが得意でも、小説がきらいだったら小説家の道は楽しめないわけです。才能を最大限活かすためにも、「好き」は大事なのです。
そして、仕上げに、自分の価値観にやりたいことを照らし、本当にやりたいことを見つけていきます。もう職業で職を探さなくて良くなるのです。職業のために自分の身を削らなくて良いのです。
また、時代が変化しても、軸が分かっているので、好きなことや実現手段だけを変えていけばいいので、精神的にも楽になります。
受験生にすごくオススメである

この本は高校生、特に受験生にオススメだと思いました。
18歳でやりたいことがわからないのは当たり前
日本では、大学に入学する前に自分のやりたいことを決めなければならない、という風潮があります。でも普通に考えて無理です。
海外の大学とかだと、途中で専攻を変えれたりします。シドニーで知り合った友人は「18歳で学びたいこと見つけるとか無理でしょ?」って言ってました。でも日本では、その考え方は浸透していません。
才能と好きのかけ算でやりたいことが決まります。
しかし、人の興味は移り変わります。私は昔、仮面ライダーや○○戦隊○○レンジャーが大好きでしたし、なりたいと思っていましたが、今は全然思いません。人の興味はどんどん移っていきます。
また、、特に目立った才能がないと思っている人もいますし、学校の洗脳で無能扱いされた人はどうしたらいいかわかりません。
大人でもやりたいことがわからない人がいるのに、一生付き合う分野を18歳で決めろというのは無理難題です。
だからこそ、この本で「自己理解」をして、やりたいことを見つけておくべきなのです。
自分に合った進路を選ぶ
「世界史」が好きだからって、歴史学者になりたいかは別です。
「英語」が好きだからって、翻訳家になりたいかは別です。
「野球」が好きだからって、プロになりたいかは別です。
高校生は「好き」だけで進路を選びがちです。
しかし、「好き」だけで選んでしまうと、「なんか違う」現象が起きやすいのです。実際、理想と現実のギャップに愕然として、大学や学部を変える人は結構多いです。
これからを担っていく高校生こそ、迷走しないように「自己理解」が必要です。
「自分と向き合う時間をとれ」なんて言われたことないでしょうし、「そんな時間とるくらいなら勉強する」と思うでしょう。
しかし、「人は秒単位で時間を節約し、年単位で時間を無駄する」という言葉があります。
今、自分を知る時間をケチると、今後の人生を無駄にしかねません。
どうあるべきか(Be)、持っているもの(have)、好きなこと(like)、できること(Do)を明確にして、軸をもつことをおすすめします。
世界一やさしい本当にやりたいことの見つけ方の感想

自分を好きになれた
他人にとやかく言われても、ぶれずに生きて行けそうです。自分の強みや価値観を認識したとき、今まで隠してきた才能を「解放していいよ」「伸ばして良いよ」と認められたような感覚でした。
開放感というか、安堵というか、なにかポジティブな感情が体の奥底から沸いてきました。
ちょうど「アナと雪の女王」のエルサが「let it go」を歌いながら今まで隠してきた力を解放していくようなイメージです。

「let it go」にはこういう歌詞があります。
I don’t care
What they’re going to say
Let the storm rage on,
The cold never bothered me anyway誰に何を言われても気にはならない
嵐よ、吹き荒れればいい。元々、寒さなんて平気だったの
It’s time to see what I can do
To test the limits and break through今こそ、何ができるか試してみる時
限界を知り、打ち破ってみる
彼女は、ずっと触った物を凍らせるという力を隠してきました。しかし、彼女の戴冠式の日に妹のアナとささいなことで喧嘩してしまい、力が暴発します。今までずっと隠してきたのに、多くの人に知られてしまい、自分の王国を飛び出してきてしまうのです。
そして、「Let it go」を歌い出すわけですが、最初は「私は孤独だ。隠さなきゃ行けなかったのに」とネガティブです。しかし途中から「もう知られてしまった。これでいいのだ。周りは気にしない。」と、どんどんふっきれて行くわけです。
自分でも認められなかった才能を素直に認め、どれくらいできるか試し始めます。最終的に氷の宮殿をつくり、王国を捨てることを決意し、容姿も開放感あふれた感じに変わっていくのです。
強みの話に戻しますと、
「短所」と「長所」は表裏一体です。自分の持っている物をどう認識し、活用していくか重要なのです。
目立った才能がないと思っていた私は、隠れていた才能を発見できたことが素直に嬉しかったし、「自分の強みを伸ばしていけばいい」という言葉に救われました。
人の強みは伸ばそうと思えば、どこまでも伸ばせます。才能だからこそ伸ばせます。氷の力を持っていない人が、どれだけ努力しても触った物を凍らせるのは無理です。
悩んでいるなら、エルサみたいにふっきれましょう。才能を認識してあげて、伸ばしまくりましょう。
自己理解をもっと学びたい

ストレングス・ファインダーという自分の強みを5つだしてくれる本を併用しました。私の強みは「規律性」「学習欲」「共感力」「親密性」「目標思考」でした。八木さんの本でも、似たような結果がでました。
なかでも「学習欲」は半端ないです。
面白いと思ったことに対して細かく学びたくなります。学問的なものだけでなく、アニメとか映画、ドラマでも細かく調べ上げたくなります。
今は、「自己理解」を学びたくてしょうがないです。心理学はもともと興味があったので、それも影響しているかもしれません。
「自己理解」は、「自分のことなのに自分のことを全然わかっていない」ことを気づかせてくれました。それが新鮮で面白いと思ったのです。
これからもじっくりじっくりやって、もっと自己理解をしていきたいし、「自己理解」を学んで人の奥深さを共有していきたいですね。
やりたいと思うことが見つかった

現時点での私の自己理解はこんな感じです。
価値観=熟達、冒険、ありのまま、快適さ、愛情(精神的な安定。自由。新しいことを体験する、学ぶ。コツコツやってその道のプロになる、完璧を目指す。)
強み=「共感力」「狭く濃く関係を築くこと」「目標に向かってコツコツやること」「学ぶこと」「自分で身の回りのことを決めること」「教えること」「自分の考えを伝えること」
情熱=エレクトーン、英会話、教育、小説執筆、ディズニー、海外ドラマ、歴史、猫(これら以外にもめっちゃありました。)
これを踏まえて、やりたいと思ったことは
・エレクトーンの個人教室(教える×エレクトーン)
・受験生向けオンラインサロン(狭く濃く関係を築く、自分の考えたことを伝える×世界史、受験)
・オンライン英会話教室(教える×英会話)
・文章力アップ教室(教える、書く×書く)
また、いろいろ学んだ後で、自分の考えを伝えるのが好きなので、情報をただまとめて発信するのはちょっと違うんじゃないかなとも感じました。
やりたいことは変わるかも知れません。しかし、自分の価値観や才能が分かっているので、不安がありません。
好きなことはどんどん変わりますが、価値観と得意なことという軸があるのでそれにあわせてやることをずらしていけばいいのです。
まとめ
まだまだ自己理解していきたいし、じっくりじっくり考えたいので、「学習欲」を抑えながら、この本を読み込んでいこうと思います。
時間をとって考える価値がありますし、自己理解は今後の人生に関わります。受験生に勧めたい一冊だと強く思います。
なかなかの長文でしたが、読んでいただきありがとうございました。ぜひ「自己理解」やってみて下さい。
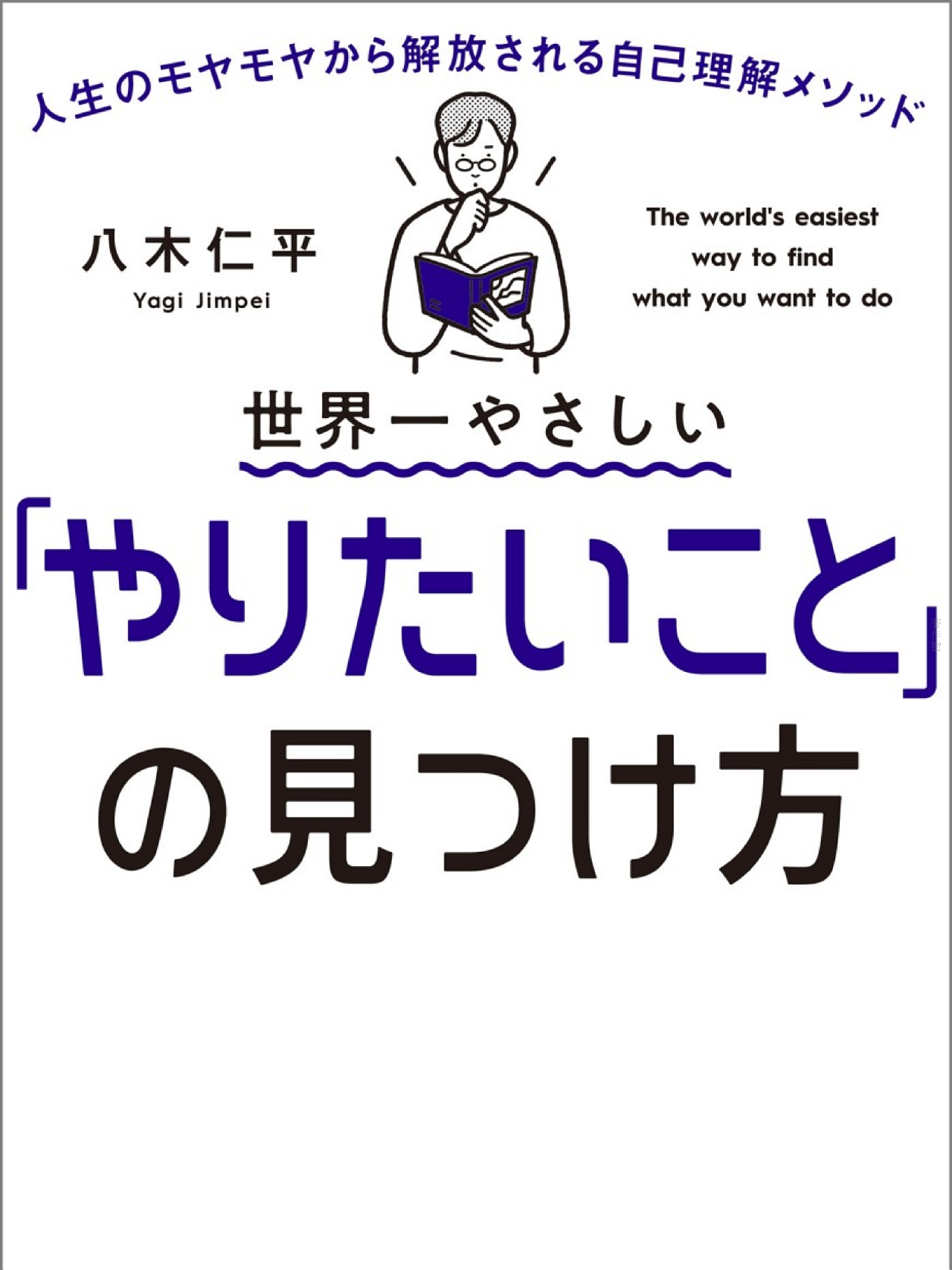


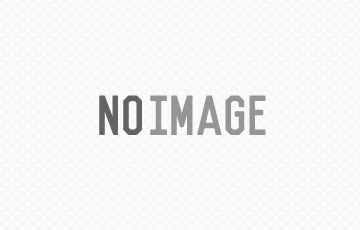





コメントを残す