はいどうも、たけうちです。
突然ですが、演劇人のそこのあなた、即興劇はお好きですか?
私は苦手です!(キッパリ)
即興劇は、「エチュード」や、「インプロヴァイゼーション(通称:インプロ)」なんかとも呼ばれるもの。
エチュードはフランス語、インプロは英語で、どちらも「即興」という意味で用いられますが、エチュードは元々音楽用語ですから、演劇で言う「即興」はインプロの方が意味としては正確なのk
まあどっちでもいいですね。
アドリブ芝居に特化したもの、人前でやる即興劇を「インプロ」「インプロショー」と言う人もいますが、一旦は置いておきます。
この記事では即興劇全般を「エチュード」と名付け、演技の練習としてやるものを指すことにします。
さて、先ほどの問いかけに戻りましょう。
繰り返しになりますが、演劇ドハまり中の私でも、エチュードは苦手です。
というのも、私は大学のときに少しだけ演劇サークルで遊んでいたことがあるんですが、全く経験のない状態でエチュードをやることになり、何を言えばいいのか分からず頭が真っ白になってしまって、劇が停滞してしまったり、観客から「え?」というちょっとした否定の声があったりして、きゃあ怖いっ、明確なトラウマとなりました。
苦手というよりは、トラウマから来る恐怖の方が大きいのかもしれません。
これを読んでいるあなたもそんな感じで「おもしろいこと言わなきゃ!」「気の利いたこと言わないといけないけど思いつかない!」で頭が真っ白になってしまったり、エチュード中の自分の提案に否定的な態度を示されたりで、エチュード怖い!苦手!と思っているではないかと考えています。
しかし、安心してください。本記事では、解決策をご提示しましょう。
私もこれを知ったことで少しずつ恐怖を和らげ、エチュードにチャレンジ&少しずつ楽しめるようになっております。
この記事では、エチュードはなぜ行うのか、ということを整理した上で、エチュードを楽しめるようになるための原理原則を解説していきます!では、いきましょう!
エチュード(即興劇)の目的
手段と目的をはき違えている人が多い

まず初めに問いたいことがあります。それは、
エチュードをやるのは、なんのためなんでしょうか。
ということです。
舞台上でセリフを忘れたとき、相手の役者が間違えたときに即応するため?
のんのん、違います。即興で芝居ができるようになるために、エチュードをやるのではありません。
ではなぜやるか?
エチュードは「様々なシチュエーションとコミュニケーションを学び、それを台本演劇に活かすため」に行うものです。
すなわち、演技訓練の一種ということですね。
「即興のための即興ではない」ということがポイントです。
私がいた劇団も、コメディというジャンルを軸にした劇団だったからか、エチュードもネタ合戦、おもしろ合戦的な要素が強く出ていました。
トラウマは上記に記載した通りですが、台本があってもアドリブやったもん勝ちという空気がありまして、(それはそれで楽しかったですが、)役者をやる時には、それがかなりプレッシャーでした。
トラウマもあいまって、おもしろいこと思いつかないし、「エチュード(アドリブ)苦手」「演劇楽しくないな~」となってしまったんですよね。
エチュードは「様々なシチュエーションとコミュニケーションを学び、それを台本演劇に活かすため」に行うもの

話を戻しますが、エチュードは役を生きる練習をするための手段のひとつ。
「役を生きる」とは何か、という話ですが、その前に、演劇とはなにかというところ。
演劇は、他者とのコミュニケーションで成り立つもの、みんなで創り上げていくものですよね。決して独りよがりなものではないですし、誰かが設定を無視して脚本に逸れた突拍子もない奇っ怪な行動していては成り立ちません。
その状況に身を置いた上で、共演者とコミュニケーションを取って物語を進めていく。それが演劇です。
その中で舞台上で実体として器として存在するのが俳優で、キャラクターを演じていく。
「役を生きる」というのは、キャラクターになった上で状況の中で相手と共鳴して、目的を達成するために行動すること。その積み重なりが物語ということになります。
「俳優の良い演技は、演技をしないこと」などと、やたらかっこいいこと言う人がいますね。
その通りだと思います。(同意なんかい)
まとめれば、「役を生きる」とは、自然体で演じられることを指します。エチュードはその「役を生きられるようになる」ための練習のひとつとして存在するものということなんです。
これが分かるだけでも、エチュードへの恐怖心が少し和らぐのではないでしょうか。
演劇は楽しんでなんぼ

役がとか、俳優がとか、それっぽいことを書いてきましたが、ただの趣味演劇人なのでね、ただ好きで勉強して、それをアウトプットしてるだけなのでね、そこはご愛嬌ということで(笑)
さて、演劇観は人それぞれあると思いますが、演劇を趣味にしている私としては、「演劇は楽しんでなんぼ」だと思ってます。
楽しくなきゃ意味がないっ!!
もっといえば、私は物事を上達させるには、「楽しい」を核にする必要があると思っていますし、つまらない、辛いと感じる物事を上達させるには限界があると思っています。
そんな、やや過激なことをつらつら語っている記事はこちら。「自分は真面目な人」と思う人ほど読んで下さいね。
楽しくなきゃ何かが間違っている
さてさて、演劇は全てが楽しく、面白いのです。んへへ。
舞台上やカメラの前の、本番の演技の瞬間や観客からの拍手、感想をもらうときだけでなく、それぞれのアイディアが自由にアウトプットされ、笑い合いながら形づくっていくその過程、なんなら仲間と雑談をしている瞬間でさえ、全部が面白いんです。
だからエチュードという練習、うまくなるための過程だって、楽しくあるべきだと思いますし、実際楽しいものなのです。
劇作家である平田オリタ氏の言葉にこんなものがあります。
「演劇とは、楽しいものです。楽しくなければ、何かが間違えているということです」
良い言葉ですよね。楽しくないのであれば、なにか原因があるはずだということ。
「演劇は子供の遊びくらい真剣なゲーム」と表現されるほど、演劇は遊びのように楽しめるもの。そう、演劇は遊びなんです。
楽しくなかったら、なにかが欠けていたり、歪んでいたり、間違っていたりするはず。
エチュードの目的を間違えているかもしれないし、エチュードをする環境を間違えてるのかもしれない。
でも、ちょっとした捉え方や、ちょっとした環境の変化で、つまらない、怖い、苦手と思っていたことが、がらっと変わることは往々にしてあります。ご安心下さい。
今楽しくない、苦手、と思っていても、あなたが楽しめるようになり、上達していけるチャンスはまだまだ転がっています。楽しめないのはあなたのせいではない。才能がないと落ち込まないで下さい。
ではいよいよ、エチュードを楽しめるようになるためにはどうすればいいのか、基本的な考え方や方法をお伝えしていきましょう。
エチュードを楽しめるようになるために理解したい基本原則

エチュードを楽しむには、まず原則を理解し、環境を整えることが肝要です。では原則とはなにか。3つあります。以下の通りです。
①安全 → 自由な発想
②否定しない → Yes, and
③楽しむ
ひとつずつ見ていきましょう。
原則その① 安全 → 自由な発想
原則その①。エチュードをする環境の安全性を確保しよう、ということです。「安全」には「身体的安全性」、「精神的(心理的)安全性」どちらも含んでいます。
というのも、『エチュードには、その性質上、「他人を傷つける可能性がある」』ということを認識しておく必要があるからです。
例えば、「急に殴られるかもしれない」とか「性的な部分に触れられるかもしれない」という恐れがあると、安心できませんよね。身体的安全性がありません。
また、身体的な接触がなくとも、勇気を出して表現したアイディアに否定的な態度や言葉をかけられる、トラウマを無理に掘り起こされたり、センシティブな話題に入りすぎるなどしても安心できませんね。そう、精神的(心理的)安全性がありません。
そういう安全性をみんなが認識し、安全性を確保した状態でエチュードに臨まないと、誰かが怪我をするわけです。
否定の3種類
精神的な安全性と関わってくるので、ここで「否定」のお話を。「否定」には3種類あることをご存知でしょうか。
それは、言語的否定、態度的否定、集団的否定の3点です。
ひとつめの言語的否定。「はあ?」とか「だめ」とか、そういった言葉としての否定。
ふたつめは態度的否定。腕組みをしたり、眉間に皺がよったり、半笑いで首をかしげたりなど表面に出る否定。
そして、みっつめは集団的否定。特定の人を省いたりする、存在の否定です。
振り返って見て下さい。あなたが、エチュードが苦手だと思った時、なにかトラウマになったときの場面を思い返すと、こうした否定があったのではないでしょうか。
それだけ、否定は攻撃力が強いもの。否定をしないこと、肯定することの認識を揃えておくことの重要性がお分かり頂けたかと思います。初心者であれば初心者であるほど、エチュードをする前の準備運動は忘れないことです。色々なワークがあるので、また別の機会にご紹介いたします。
安全性が自由な発想につながる
さて、こういった安全性がないと、傷つく、トラウマになる、のはもちろん、人間は「失敗できない」と感じやすいものです。
失敗できないと、自由な発想を表現できず、「正解」のものだけ選んでしまうようになります。脳にフィルターをかけている状態ですよね。
そうすると表現としてはとても閉じてしまうし、それが続けば自由な発想すら生まれなくなってしまう恐れがあります。
裏を返せば、創造的な発想は失敗が許容される、むしろ歓迎される環境でこそ生まれる、ということでもあります。
繰り返しになりますが、安全性が土台にあるということを全員が共通認識で場をつくり、場を暖めることが大切。
こうした場があることで、安心してチャレンジして失敗できますし、自由な発想が生まれやすく、共演者同士の表現と表現が掛け合わさって素晴らしい化学反応が起こります。
そして面白いことに、真剣に取り組みチャレンジした先の失敗というのは、見応えがあるものです。そう、失敗には価値があるのです。「挑戦して失敗しよう。次はもっと上手く失敗しよう」こんな言葉があるくらいですからね。
安全な場ができたら、失敗しに行くくらいの気持ちで飛び込んでいきましょう。
②否定しない → Yes, and
①がとても大事なので、詳しく書いてしまいました。そして、「原則」と言っているのに、少し要素が被っている部分があります(笑)お許しください。
原則の②は、「否定しない」ことです。
先ほど否定の3種ということをお伝えしましたが、ここでの「否定しない」というのは「共演者の意図を否定せず受け入れること」を指します。
相手の提案に「Yes!」をするということですね。
そして、エチュードを発展させていくためには、相手の提案を受け入れたあとで、自分の発想を足して返してあげることが大切です。これを、「Yes, and ing」と言ったりします。
例えば、「おかーさーん!」と入ってきた息子役がいたとして、共演者は、(息子役の演技にもよりますが)「だれなの?息子はいないわよ」と返さないこと。
これでは「No」を突き返してしまっていますね。
そうではなく、「どうしたの?息子よ!あら怪我してるじゃない!」と返してあげる。
「Yes(息子という関係を受け入れる)」+「and(怪我しているという新たな要素を足す)」になっていますよね。
こうして、発想のバトンを繋いていき、エチュードが進んでいくという訳です。
そして、発想をアウトプットするときは、躊躇しないことです。脳の検閲をせずに、浮かんだままにアウトプットしていきましょう。これが創造の第一歩です。
脳の検閲を外していくためのトレーニングとしては色々ありますが、そのひとつとして、家でひとりでもできる独り言トレーニングというのがあります。参考にしてみてください。
*日記がテーマになっていますが、トレーニング内容だけ読んで下さいね
③楽しむ
安全な場ができた、肯定しあって発想が飛び交っている空間ができた、その次、最後の原則③は「楽しむ」ですね。
これは言葉通りです。安全な場で、自由な発想が飛び交う場。この前提条件が揃っていると、めちゃめちゃ怖いという感情はなくなります。緊張とかドキドキ感、スリルはありますけどね。
それでも、考えずに発想を出し合っていると、劇が転がるように進んでいく快感を味わえるはずです。スキルもドキドキも楽しむ気持ちでやってみましょう。
エチュードの基本的な流れは下記しますが、ここまででもお伝えしている通り、特別な発想は不要です。
その場で出たお互いの表現を使って、仕掛けたり、乗っかったりしていくだけ。
そう、変にボケなくて良いし、かっこいいこと言おうとしなくていいんです。それは芸人さんに任せましょう。
普通の発想と普通の発想だけで十分に面白いし、楽しめるのです。
エチュードの流れが分かれば怖くない

エチュードの基本原則が分かったところですが、「やっぱり怖いな」という気持ちが拭えないそこのあなた。まあ読んでいるだけでは頭では理解できても、心は正直です。
台本とは違って、このあとどうなっていくのか分からない不安もありますしね。。
でもご安心下さい。エチュードには、流れがあります。流れを分かっておくと、お先真っ暗ではなくなります。では、エチュードの流れとは?それは、こちらの3段階。
オープニング→ゲーム→オチ
です。
エチュードの準備
それぞれの段階を解説する前に、準備から。
まずはエチュードをする人数。
これは2人から始めて行きましょう。3人以上になると、いろんな役割を考えながら、複数の共演者のことを考えながら、とよりマルチタスクが増えるので、やることがより高度になりがちです。2人でやっていきましょう。
次にお題。
共演者が決まったら、観客から「お題」をもらいます。
ここの状況設定の仕方は、役柄ももらう(宇宙飛行士と科学者)、どんな状況かももらう(宇宙に行くのを嫌がる宇宙飛行士とそれをなだめる科学者)など、様々ありますが、本稿では「ピンチ」や「ナイトクラブ」など、基礎となるお題だけをもらうという想定で解説していきます。
①立ち上げ(オープニング)
では、最初は立ち上げ。お題をもらったら、アイディアを思いついた方から始めて行きましょう。
最初は、その2人の関係性が分かるように、多少説明的でも良いのでセリフや動きで、ざっくりと立ち上げていきます。
例えば、「ピンチ」というお題をもらったとすると、、、
A「あちゃーどうしよう!やっちゃったー!」
B「どうしたのお母さん!」
A「焼いてたパンケーキ10枚床に落としちゃった」
B「ええ、落としちゃったの?」
A「そう、フライパンもまっぷたつ」
B「あちゃー、これからパーティーなのに!」
どこで、誰と誰がいて、どんな関係かが分かりますね。
何やら、家のキッチンでのお母さんとその子供のやりとりで、これからパーティーなのにパンケーキが台無しだと。お、なにかが始まりそうだと、観客はワクワクするわけです。
ちなみに、Aの「パンケーキを落としてしまった」という要素にBが「これからパーティーなのに」という要素を付け加えてますね。「Yes,and ing」です!
②ゲーム(展開・主題)
さて状況が立ち上がりました。この状況を使って何を巡る物語か?が展開していく段階です。何かが起こる状況を作るためには、ここでも「Yes, and ing」です。
例えば先ほどの例を使うと、
B「お母さん!パンケーキの材料を買ってきたよ。卵と、牛乳と、」
A「ありがとう、あれでも、これウズラの卵じゃない?」
B「え?ウズラじゃなかった?あ、ダチョウの方がよかった?」
A「あ、ダチョウね、大きいからそれでもいいけど、、、、」
B「え、なんの卵がよかったの」
A「ほら、、、、ニワトリ」
B「ニワトリ?ニワトリってなに?」
A「えーっとニワトリってのは、ヒヨコの大きいバージョンで、、、」
B「え、あの黄色いの大きくなるの?!」
パンケーキの材料を買ってきたBに対して、「ウズラの卵」という要素を足すA。さらに「ダチョウの卵」と乗っかった上で、「ニワトリを知らない」という要素足すB。
こんな具合です。
そうすると、「お母さんがニワトリを知らない子供に対して「ニワトリとはなにか」を一生懸命説明する」というゲームが始まるわけです。
別に特別な発想は使っていないのに、面白く発展しているのがわかりますよね。
正当化してしまおう!
大事なのは、出てきた情報を“正当化する”という姿勢です。
上記の例で言えば、パンケーキの材料にウズラの卵買ってくる子供がいたら、「ニワトリを知らない」ということにしてしまうんです。都合がいいけど、「Yes,and ing」はそういうことです。
他にも、水族館にパンダがいたとしても「経営難の水族館なんだ!」ということにすればいいし、ダイエットで亀をひたすらに投げている光景があるならば、伝説の師匠から教わった、ということにすればいい。
『思いついたアイディアがどんなに突拍子もないものだったとしても正当化してしまえばいい』と思えば、自分も相手も思いついたことを臆さず出せますし、安心してどんどんと創造的に発展させることができますよね。
③オチ(終わり)
立ち上がり、ゲームと来て、最後にはオチが来ますが、エチュードにおいて、「完璧な落としどころ」を決める必要はありません。芸人さんみたいに、笑いどころを無理につくることはないのです。
変化が生まれて、空気が変わったら、そこがオチになり得ます。なにかが決まったり、動いたりしたときがオチになりやすいです。
例えば、先ほどのパンケーキ親子の、「ニワトリがなにか」を教えるゲームのあとだったら、
A「ニワトリを捕まえてきて、卵をゲットすればいいのよ」
B「ああそうか、分かった!じゃあ行ってくるね!」
Bが退場
これでオチになります。大層なオチはつけなくて良いですし、独りで決めなくていいものです。
エチュードは、共演者と一緒に流れを育てていくもの。受け入れて、足して、進めることを繰り返して、呼吸のように流れていきましょう。
エチュードは“役を生きる”ための練習になる

ここまでエチュードの基本原則や流れについてご紹介してきました。
ここで改めて目的に立ち返っていきます。エチュードはなぜやるかといえば、「役を生きるための練習のため」というものでしたよね。
セリフをセリフのまま読むな
台本のある演技では、登場人物の関係性やセリフはすでに書かれています。
でも、その状況下で「どう感じて」「どう反応するか」までは、俳優の感性に委ねられている部分が多くあります。
そしてそういった部分は、セリフ外での振る舞いや、相手への反応に大きく現われてくるもの。同じ役でも、演じる俳優によって表現が違うのは、そういうところがあるからです。
また、俳優をやっていると「セリフをセリフのまま読むな!」というのはよく言われることです。
例えば、好意的な「おはよう!」というセリフの中には、「仲良くしようよ」という意味が込められているかもしれませんし、しみじみとした「どこに行こうか」というセリフの中には、「もっと一緒にいたいな」という意味が込められているかもしれません。
台本演劇では、それぞれの役に「こうしたい」という目的があり、役は目的に基づいて行動をしていきます。そこから出てくるセリフは、その役の意図から出てきたものであり、台本に書かれたセリフをそのまま読んでいるものではないわけです。
シチュエーション × 関係性
エチュードをすることによって、こうした役を生きるための感性が鍛わります。
・そのシチュエーションに置かれたとき
・相手との関係性の中で
・自分の中からどんな感情や行動が自然と湧き出るのか
こうした様々な状況下、相手との関係の中で、どう生きるのか、というところを、繰り返し楽しみながら反復していくことで、役の目的を感覚的に理解し、行動する、すなわち「役を生きる」感覚をつかんでいけるのです。
どう?エチュードやりたくなりました?さあ、チャレンジしてみましょう!
まとめ
まとめると、
パンケーキ親子の例は、実際私がやったエチュードでした。ニワトリ知らない子供やるの楽しかったです。
以上です。







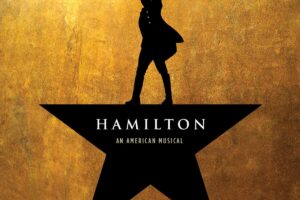


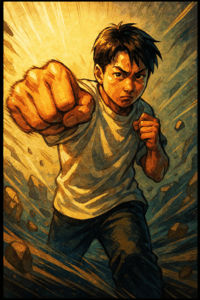
コメントを残す