こんにちは、タケウチです。
ひとつのことを極められるスペシャリストと、いろいろなことができるゼネラリスト。どっちがいいのだろう、どちらが社会で活躍できるのだろう、自分はどちらで成功するにはどうすればいいのだろう。悩みますよね。
今回は、最近の気づきも含めて、エッセイ的にスペシャリストとゼネラリストを分析していきます。
スペシャリスト的な生き方の魅力と課題

魅力
特定の分野に集中し、深い知識やスキルを磨くことで、他の人にはできない価値を生み出せる。
長期的に一貫性があり、プロフェッショナルとしてのキャリアを築きやすい。
課題
突き詰める過程で、プレッシャーや飽き、自己否定感に直面しやすい。
他の興味を犠牲にする必要がある場合がある。
ゼネラリスト的な生き方の魅力と課題

魅力
多様な興味やスキルを持つことで、柔軟性が高くなり、さまざまな場面で活躍できる。
一つの分野に飽きても、新しいことに挑戦しやすい。
「ちょっと楽しい」を積み重ねることで、楽しさを軸に成長していける。
課題
ひとつのことに深く没頭する時間が短くなりがちで、「プロレベル」まで達するには時間がかかる可能性がある。
周囲と比較して「自分は突き抜けていない」と感じやすい。
社会がもてはやす「スペシャリスト」会社が求める「ゼネラリスト」

社会がもてはやすスペシャリスト
プロとして活躍しやすいスペシャリスト。いわゆる「成功者」にはスペシャリストが多いのではないでしょうか。「好きなことを突き詰める」とか「これにしか夢中になれなかった」とか、そんな風な哲学を、メディアが「素晴らしいもの」としてラベル付けしている傾向にあると思います。
会社が求めるゼネラリスト
一方で、会社というのは従業員に対して、ゼネラリスト的であることを求める傾向にあると感じています。
苦手分野の許容度が低く、例えばリーダーシップとかファシリテート力とか、集中力とか分析力とか、苦手を克服させようとしてくる職場もあるでしょう。(もちろん適性を常に鑑みて適正配置してくれる職場もあります)
逆に言えば、私みたいに「これといって夢中になれるものがない人」や、「いろんな分野に興味のある人」、いろいろやってみたい人にはうってつけの場所でもあるということです。
私は、目指すべき目標や姿を決めてしまうと、「こうしなければ」が強くなりすぎてしんどくなってしまうタイプ。(多分これまでの生育環境や心理的課題も影響しています)
また、これまでいろんな分野に手を出して、途中で飽きたり、まあとりあえず満足という状態になって、そこから突き詰めたりはしなかった経験から、私はいろいろやる方が得意なゼネラリストタイプだと分析しています。
強みとしては、いろんなものに興味があって「好奇心旺盛」というところと、いろいろやってどれも比較的こなせる「器用さ」が突き抜けているというところでしょうか。
ゼネラリストだからといって「突き抜けているところがないわけではない」というのは最近気づいたところです。
というのも、今の仕事で採用と広報に関わっており、2つの領域の橋渡し的な役割をしているわけですが、「あっ楽しいわ、向いてるかも」と思ったのがきっかけです。広報の面から見た採用と、採用の面から見た広報。2つの領域にいるからこそ分かることや、連携がスムーズになることを実感しました。
多分、あなたは今後ずっと「人事ね」とか「広報ね」とか言われていたら、それをやっていくのに自分に足りていない部分がだんだん見えてきてしまって、「無理だろうな」とか、「あー飽きたな」とか感じてしまっていたことでしょう。
とすればスペシャリスト的な人には苦しいですよね。突き抜けているところがあって、逆にそうでないところは致命的。
自分の突き抜けたところを上手に活かせて成功できた人が、過去を振り返るときに「学校や職場では結果の出せる人間じゃなかった」とか、「特定の作業に時間がかかりすぎてみんなからバカにされていた」とか、そんなお話がよく出てくるかと思います。
自分の特性を認めてあげよう

スペシャリストに憧れて苦しかった
メディアを見ているとスペシャリスト至上主義がはびこっているように思えてきます。物事を突き詰めて成功すべきというメッセージをどうしても受け取ってしまう。
私は長らくスペシャリストになりたくて、でもできなくて、めちゃめちゃ苦しかったです。私はいつも目標から決めて、それに向かってどうすればいいか、どうすべきかを考える癖がありました。
目標を決める時に憧れから入ることも多く、「京大に入りたい」とか「俳優になりたい」とか、これといってやりたい研究分野があったり、演技はやったことなかったりすることもありました。
憧れから入ることが悪いことではありませんが、私的には興味が向いたことをやって、「これはやっていて楽しい」を積み重ねた結果、高いレベルに来ていた、その結果「○○向いてるかも」「○○になれるかも」「チャレンジしてみよう」の方がしっくりくる感じがします。
でも上記の話はスペシャリスト的な話になりそうですね。難しいです。
要はスペシャリスト的要素と、ゼネラリスト的要素のバランスで、どちらの要素が多く見られるのか、じゃあそれを活かすにはどうすればいいのかを考えるのが肝要なんですかね。
自分を認める
ゼネラリストだって良いじゃないと思えるようになったのは、上述した職場での出来事があったから。
自分の適性を認められるようになり始めて、「決めなくてもいいじゃない」「流れに身を任せても良いじゃない」と、思考の余白をつくれるようになりました。
それにひとつを突き詰めるのが苦手だからって、世にいう「成功」を掴めないわけではありません。
器用にいろいろこなしてきたからこそ、広い視野を活かして特定の分野で成功したり、分野と分野を掛け合わせて新しいモノを生み出したりすることもあるかもしれません。
まとめ
後半は最近の私の心の変化で、スペシャリスト、ゼネラリストの話からだいぶ逸れてしまいましたが、同じようなことに悩んでいたあなたの心が少しでも柔らかになっていたのなら幸いです。
自分を認めて、自分らしく。
それではまた。









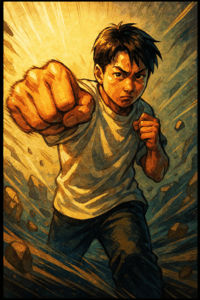
コメントを残す