どーもー、たけうちです。
時々やるツラツラ文章。最近やってませんでしたが今日はやります。ツラツラ文章は、特にターゲット決めずに、SEOも全く気にせずに、最近気づいたことを書いていくだけのエッセイ記事のことです。
言ってしまえばネットの海からこのサイトに来てくれた人が、目当ての記事を読んだあとで、タイトル見て「これ読んでみたーい」と回遊させるための記事です。
さらに言ってしまえば!(もういいね)
さて、今回は「人は観てきたものでできている」ということをテーマに、最近の気づきを書いていきます。
人は観てきたものでできている

「人は食べたものでできている」というのは、ダイエッターがよく言っている言葉だと思います。ラーメンを毎日食べていればそんな身体になるし、栄養に気を遣っていれば、思うとおりの身体になる、的なことですよね。
私は「当たり前やん」と斜に構えるタイプの非ダイエッターですが、一方舞台人としてはよく思うことはあります。
それは「人は観てきたものでできている」です。
観てきたものの引き出し
こないだ参加した演技ワークショップの中で、こんなワークをやりました。
「同僚で飲み会をしている」というなにげないシーンを作る
→そのシーンを○○風にするために、同じシーンに要素を足してみる
というワークです。
例えば、アメリカのホームコメディ風にしてみる、とか、サスペンス風にしてみる、だとか。
それでね、特にサスペンスが難しかったんですよ。
ホームコメディは、割と結構好きで見ているのもあり、すぐに身振り手振りとか、ありそうなセリフとかを自分の中から引っ張り出せたのですが、サスペンスはそうはいかず。
というのも、サスペンスを最後に観たのいつなん?ってレベルであり、最近インプットしてなかったなあと。
でも、他の受講者さんの思うサスペンス要素を見て「あ~たしかに」とはなるわけです。例えば、「○○がいないけど、どこに行ったの?」とか、「あのとき一人っきりで、なにをしてたの、、、?」とか、「そもそも○○って誰だっけ、、、」とかね。
「たしかに」と思うということは、それはすなわち「引き出せなかったけど、触れてきたものではあった」ということなんですよね。
俳優だけでなく表現者として、「色々なものにたくさん触れること」、そして「触れたものに対して深く理解し、引き出せるように試行すること」の大切さを学びました。
俳優に絞らなかったのは、音楽の世界でも、物書きの世界でも、やっぱりそうだよなあと思うからです。
エレクトーンやアカペラやってましたけど、上手い人って色んなジャンル聴いてるし、ピアノ奏者でもロックに詳しかったりとかしますし。
コンテンツマーケティングのインターンシップ行った時も、その時の上司が「たくさん読んで真似すると良いよ」と言っていたよなあと。
さらに私が尊敬するホラー小説家のスティーブン・キングも同じように「大量に読んで、大量に書け」って言ってたなあと。
好きなものばっかり見がちになりますし、アウトプットは面倒くさくなりがち。でも、
食わず嫌いをやめて、触れてみる。
読んで終わり、聴いて終わり、見て終わりではなく、印象に残ったこと感じたことを書き留めてみる。
本当に基本的なことを大切にするだけで感性は磨かれていくのだと思います。
演劇、音楽、物書き。私も表現者のひとりとして大切にしようと思いました。
「人は観てきたものでできている」ってどこで触れたんだっけ
それで、タイトルにもある「人は観てきたものでできている」っていう言葉を、ワーク中に思い出して、自分の中でリンクしたわけですが、この言葉ってどこで触れたんだっけ問題。
これも「観てきたもの」ですね。
ワークのあと、うんうん考えながら、ボクシングジムに行って乱れるように打ち、転職フェアに行き、帰りにラーメン食べても、全然思い出せず。
それでその1週間後くらいですかね、電車に揺られて車窓眺めているときにようやくふっと「あ、あれだ。」と思い出しました。
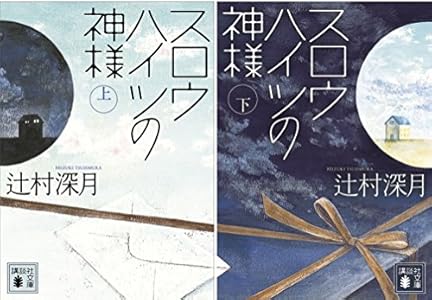
これ。私が大好きな辻村深月氏の「スロウハイツの神様」という作品。売れっ子の脚本家、小説家、駆け出しの俳優、漫画家、画家、映画監督の卵、が同じアパートで暮らしている、というお話。
まあ、トキワ荘的な感じですよね。辻村氏がドラえもん大好きだからね。辻村氏らしいなあと思いながら二年くらいに読んだ記憶。
今小説が手元にないので内容はだいぶうろ覚えですし、「観てきたものでできている」というのが作中の表現として書かれていたのか、読後に自分が感じただけだったのかも曖昧です(笑)
まあそれはどちらにしろ、なぜ「観てきたものでできている」という言葉が印象に残っているかといえば、この小説には、登場人物に表現者がたくさん出てくるわけです。
そして、それぞれの登場人物の表現が、登場人物同士影響しあっている、というところがミソでした。
例えば、環という主人公は、今は同じアパートに住んでいるチヨダコーキの小説を読んで、過去に心救われていますし、
ある事件をきっかけに筆を執れなくなったチヨダコーキは、苦境でも健気に、そして脚本に反映しようとする環の意志に心打たれ、再び小説を書こうと決心します。
それまで触れてきたものが信念をつくり、その人の創作、表現に反映されていく。まさにそれですよね。
しかしこうやって、一回読んだ小説の表現が、数年経って、とあることをきっかけに浮上してくるのはとても興味深いなあとも思います。ふとしたことが意外なところで紐付き、繋がってくる。面白いですよね。
あ、もしかしてこのエッセイ自体が、数年後の誰かの“観てきたもの”になって、その人をつくるかもしれないって考え、うへへへへへへ。
ジャンルは違えど、なんやかんや20年くらい表現者をやっている者として、今後も感性を磨きつつ、様々ことを見ていきたいと思いました。
まとめ
まとめると、
これだから表現者はやめられねえってばよ
以上です。
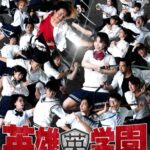

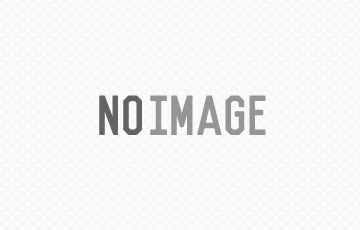







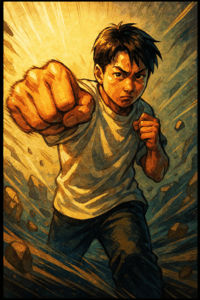
コメントを残す